森瑶子の思いで 5
年上の人が機嫌よくアメリカへ帰ってからも、作家森瑶子は次々に作品を発表し、その多作さは天を突く龍のような勢いで加速がついていた。
私は始めてのTVドラマを経験する事になった。 宇野千代先生のベストセラー「生きてゆく私」で主演女優十朱幸代さんの衣装を担当する事になったのだ。 今と違いTVドラマに私のようなCFのスタイリストが付くことは珍しく、十朱さんの強力推薦があって実現したのだと思う。
ハリウッドとは雲泥の差で1ヶ月前からスタンバイしていてもどんどん本が遅れるので、日本のスタッフや女優さんの平然としている度胸には仰天したものだ。 衣装さんと呼ばれる裏方の人々が顔色ひとつ変えず黙々と完徹してでも全脇役やエキストラの衣装を1週間で揃える努力に、広告の世界からポッと出ていって主役だけ担当する等とは大変不謹慎なのではないかと恥じ入ったものだ。 映画もそうだが裏方の人々の置かれる環境は非常に厳しく、情熱だけが彼等の支えなのだが、結局それにおんぶしている業界・・・日本に文化は育ちにくいな・・・と溜め息の連続だった。
そんな御縁で十朱さんの次のお仕事が森さんの原作だった事から、ぜひ森さんに御会いしたい、紹介して欲しいと頼まれた。 女優さんは勉強熱心なのだ。
森瑶子さんの自宅に初めて電話を入れた。
「君、今何時だと思って居るのかね?」 ミスターブラッキンは電話口で妻の不在を告げた後私に尋ね、「10時半です。」と答えると「人の家に電話を掛けるのには遅い時間だとは思わないか?」 私は恐れ入って謝り電話を切った。 うっかりイギリス紳士の気難しさを忘れていたのだ。 10分と経たない内に森さんから電話があり、事情を詫びる私に笑い乍ら「彼は道理を重んじる人だから」と軽く受け流してくれた。 私のおそるおそるのお願いに「構わないわよ、ぜひお逢いしたいし。 只、彼がもうすぐスキーに行くからその時ならゆっくり出来て好都合なんだけど、いかが?」 願っても無い申し出でだった。
84年の2月、芸術座が刎ねてから、我が家の1階のバーで十朱さんと森さんが御会いする約束が成立した。 夜型の私に例外を作って下さったのだ。
ウキウキしてその日を待つと何と朝から10年振りの大雪、心配になって自宅に電話をすると「全然平気よ、この間スイスで買って来た毛皮の帽子とブーツがあるから、それを履いてゆくから」と元気に答えて張り子の虎の私をからかった。 雪の中を颯爽と現れた瑶子さんは一段と大人の魅力に満ち溢れて当時の若い女子アシスタント達から拍手で迎えられたほどだ。
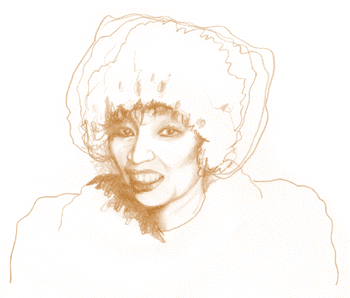 十朱さんと森瑶子さんの会合は成功し、夜が更けるまで楽しい会話がはずんだ。
十朱さんと森瑶子さんの会合は成功し、夜が更けるまで楽しい会話がはずんだ。
「このお箸素敵、何処の? 京都? 真似してもいい?」と森さんは可愛く聞きメモを書いていた。 胡麻竹に紅がらで彩色を施してある会席膳に似合う繊細な箸である。(没後出版された回顧記念の本の最後に愛用の茶わんと箸の写真が載っており、それが胡麻竹の箸であったことに胸を衝く思いがした)
「香港に取材に行こう!」としきりに誘われたのが不思議だったけれど、スケジュールがままならずお断りしたのが残念だった。
その夜は3人で熱心にお互いの人生観について話し合い盛り上がったのだった。
幸代さんも私も各々にサイン入りの著書を頂き大感激、『贈呈』の文字に心が踊った。 作者直じきに本を贈られる栄誉を初体験したのだ。 「夜光虫」という森さんの心の葛藤を書いた本で、読むのが恐かったので暫く本棚に飾って置いた。 読者としては落第点だった私。
瞬く間にまた8年が過ぎ・・・息子は大学2年からパリへ留学し、仕事に就いて私の責任は少し軽くなつていた。
森さんはどんどん公の人となり、遠慮もあり気軽に声をかけられなくなっていたが必要な時に思い切って電話をすると秘書の方が2時ならお電話を受けられる旨伝えて下さる。 時間ピッタリに瑶子さん自身が受話器を取ってくれるのだ、電話の側にいて待ってくれている誠実さに頭が下がった。 そして後日秘書の方を通じ依頼された用件は無事済んだでしょうか?と確認のお電話まで頂くのだ、お願いした私が忘れている様な小さなことにも手抜きは無かった。 そうなると申し訳無さが先にたち、忙しい瑶子さんを煩わせるなんて罪悪に等しいと思うようになっていった。
パルコで写真を一諸に撮った時は虫の知らせというのか、これっきり逢えないのではないかと、漠然と感じていた。 当時、私の方に病気の心配があり、秘かに引退を決意していたからだ。 パルコへはこっそりお別れに行ったつもりだったのだ。 ・・・ところが予感は思いがけない方向で現実と成ってしまった・・・。
瑶子さんは「忙しい?」と尋ね、私が頭を振ると「日本はプロが育たないから」と慰めるように呟いた。
『風と共に去りぬ』の翻訳に入る直前だったようだ。 その仕事がいかにハードだったかは完成した作品を読むとよく判る・・・、瑶子さんの情熱がスカ−レットと完全に同化しているのだ。
7月6日の訃報を聞いた時私は、何が彼女に起きたのか理解できなかった。 小麦色に日焼けした健康そうな瑶子さんとパルコで逢ってから2年しか経っていないのに・・・。
カサブランカの花束をゴトウから届けさせるのが精一杯、お別れに行く事はどうしても出来なかった。 私には、世間が言うような見事とか華麗な引き際とかの表現が納得出来ず、理不尽な虚無感に襲われ、時代の共有感、闘う同志として密かに信頼を寄せていたお手本が消え去る事は自分の死に等しい、とさえ思い詰めた。 TVに映しだされた御葬式は華麗で私の思いとは懸け離れたセレモニーとして進められていた。
その夜夢を見た。 若い女の人達に囲まれて宴会してる瑶子さんが私を人混みの中から目敏く見つけると駆け寄って来て、「ぱとら! いい? 痩せてきたら駄目だからね、痩せたら注意よ!」ニッコリ笑って宴会のテーブルへ戻りながら楽しいから心配しないでと言うように手を振ったのだ。 霊夢だと信じたい、幸せそうだったのが救いだった。
痩せていた私が太り始めたのは夢の中の瑶子さんの言葉に因るところが大きい。 逢う度に、口癖のように「もっと大人に成りなさい、」と言われ続けた私。 そんな言葉を掛けてくれる人は彼女以外いなかった。 あらゆる意味で大切なお手本だった人、忘れることなどできはしない。