森瑶子の思いで 3
青山の事務所時代は、TVコマーシャルの裏方として多忙な日々を送った。 モデル選びからロケ場所の交渉、衣装探しはもちろん、スタッフの足の確保、弁当の手配等、製作会社のする仕事までカバーしなければならなかった。 代理店・製作会社・カメラマン・タレント事務所全てが熱中時代。 手抜かりがあるとスタイリストに八つ当たりが集中するので、むしろ全部を把握したほうが仕事が速く、スムーズだった。 ムービーは兎も角、平面と呼ばれたスチル写真では、カメラマンが現場に入る迄に不可能な事でも可能にして待機せねばならなかったし、有名カメラマンは打ち合わせの時間を取るのにも苦労したので、作品を検討し周辺をリサーチして性格まで調べないと上手く行かない。 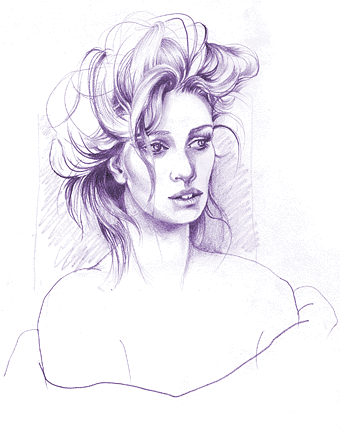 私は結局約25年間スタイリストを続けたが、あらゆる意味で本当に過酷な職業だった。
私は結局約25年間スタイリストを続けたが、あらゆる意味で本当に過酷な職業だった。
そんなある日私はミセス・ブラッキンとなっていたマコから自宅に招待されたのだ、「スタイリストについてぜひお話が聞きたいのよ」 華やかな外見とはうらはらに、忙しいだけの現実を抱えていた32歳の私は疲れて消耗しきっていた。
私とマコを引き合わせてくれた友人はべべと呼ばれていた美人で、仕事は洋裁、Mやアメリカへ嫁いだ年上の人の共通の親友だった。 ジロー時代は顔見知り程度で年下の私は相手にされなかった。
青山の事務所から15分程の旧テレ朝通りを下り、スーパーの角を左に坂を降りたところがミスター&ミセス・ブラッキンの当時の家だった。
にこやかに出迎えてくれたマコは記憶より大きくはなく、少し丸く感じられた。 「噂には良く聞くのだけど、こうしてお会いするのは初めてね、良く来て下さったわね」 腕を取らぬばかりに招き入れると、居間に居た御主人のブラッキン氏に紹介してくれた。 御主人の手前ジローでデート中眺めていたことは勿論黙っていた。 氏は当時外資系広告代理店にいらしたが、ダーツの販売代理を始めたばかりで、スタイリストに貸し出すから宣伝して欲しい、という事が本日のお招きの主旨だった。 雑誌のスタイリストとは違い、仕事が広告なのでなかなか自由が利かない旨お話すると、すぐその話題は打ち切られた。 申し訳ないような気まずい気分をマコが賑やかに打ち消しながら気配りを見せていた。 ディナーテーブルには若鶏の白ワイン煮と牡蠣とホウレン草のパン粉焼、美味しそうで、お腹が鳴った記憶がある。 湯のみに葡萄酒を注いでマコが渡してくれる。 日本の焼き物とロゼワインの組み合わせが私には新鮮で興味深く、とても素敵!と誉めると、ブラッキン氏は「ワインを湯のみでなんか僕はご免だね、ワインに相応しいグラスがあるだろう? マコ、そこのグラスを僕にとってくれないか?」と英語でマコに言いジロリと私を睨んだ。 此処へ招かれてから、マコは完璧な主婦ぶりで、たえず御主人を気づかい用件もどちらかと言えば御主人の仕事のためだったのに、内心、何故日本の女性を妻にする外国人は気難しい人が多いのだろう? と年上の人とマコを重ねて、彼女達の為にムッとしたのを覚えている。 「私、この湯のみでいいわ!」「私も!」ベベも叫んだ。 後は何を話したか思い出せないが、お食事はとても美味しかった。 こうして話をしてみると改めてマコはとても良い声をしていて、私のような断定的物言いもせず、オズオズとしながらも適切な語彙を使う気配りの人だった。 翻訳本に挿し絵も描いていて外国の漫画のような洒落たタッチに舌を巻いた。 本気になったらどんな力を発揮するだろうかと恐いような気もした。 途中4歳くらいの女の子が降りてきてぐずると優しく抱き締めて、小声で話し掛けていた。
食事が済むと御主人は女共の会話に飽きて、同席していた学生とダ−ツを競い初めた。 私達は懐かしいMや憧れの年上の人の噂・・・離婚したらしい・・・事などお互いの情報に花をさかせ、そして誰からとも無く「・・・・・」深い溜め息をついたものだ。
私が仕事をする喜びと引き換えに失ってしまった何かをマコはまだ持っていて、一方、当時まだ文章を書くという表現手段を見いだしていなかった彼女は私の独立を羨んだ。 全然幸せじゃない自分を感じて何と答えて良いか、返事に困った。
再会を約束しながら歳月だけが無為に過ぎた。 私は益々仕事に励み、コンテを描く機会もあったがダ−ツを使うシチュエーションは現れないまま記憶から消えていった。 マコには御馳走損をさせてしまったことになる。